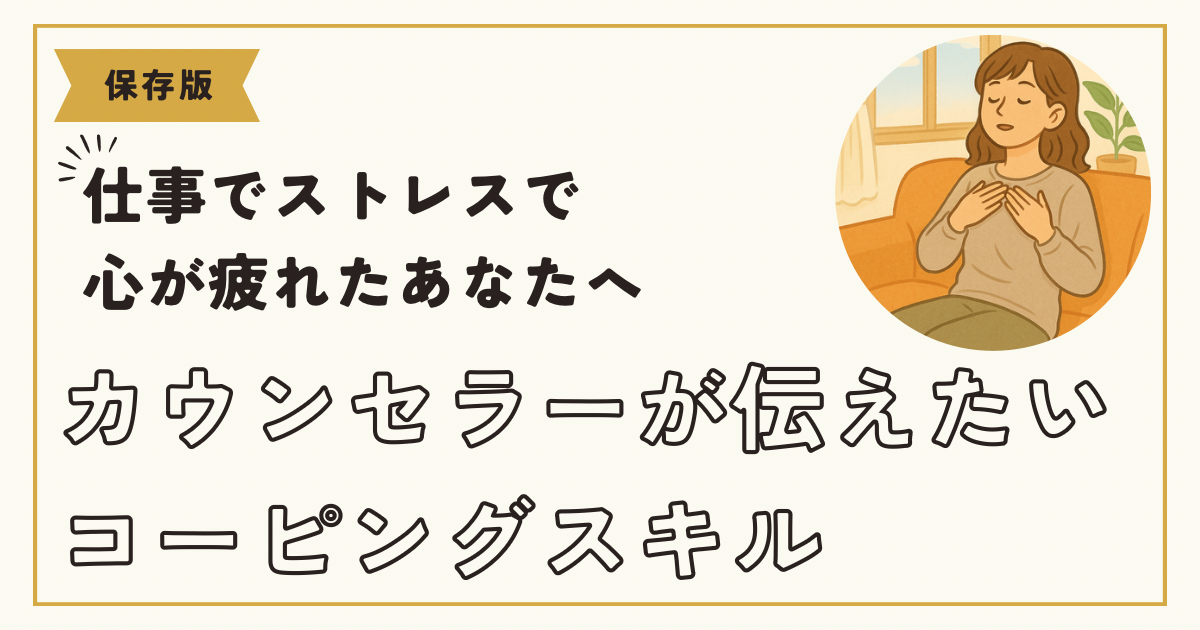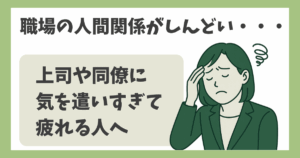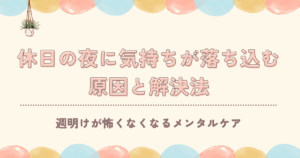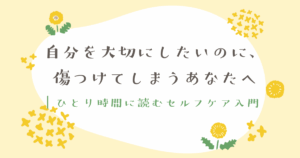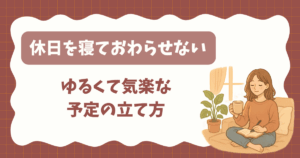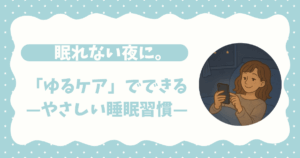「仕事がつらい…」「こころが疲れた…」
そんなふうに感じていませんか?
ストレス社会で働く私たちにとって、
仕事の責任、人間関係、将来への不安…。
毎日のプレッシャーが、こころをじわじわと締めつけていきます。
この記事では、こころが疲れたときにすぐ実践できる
「コーピングスキル(ストレス対処法)」をご紹介します。
コーピングとは?—ストレスと上手につきあう方法—
「コーピング(Coping)」とは、
ストレスの原因や反応に対して、
自分なりに対処する行動や考え方のこと。
つまり、心のセルフケア術です。
ストレスを完全になくすことは難しいですが、
どう付き合うかを知るだけで、こころはぐっと軽くなりますよ。
代表的な2つのコーピング
| 種類 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 問題焦点型 | ストレスの原因にアプローチすること | 業務の見直し/相談/学び直し |
| 情動焦点型 | 感情を落ち着けて気分をリセットすること | 気分転換/深呼吸/誰かに話す |
状況に応じて、
この2つをバランスよく使い分けることが大切です。
STEP1|自分の「ストレスのサイン」に気づこう
まずは、あなた自身の「ストレスのサイン」に目を向けてみましょう。
- 最近、眠りが浅い
- 朝起きるのがつらい
- 小さなことでイライラする
- 頭痛や肩こりが続いている
これらは、
こころやからだがストレスを感じていることを伝えてくれている大切なサイン。
まずは、サインに気づくところから始めましょう。
STEP2|心を整える「情動焦点型コーピング」5選
1. モヤモヤを吐き出す
信頼できる人に話すだけで、
こころの中のモヤモヤが軽くなることがあります。
「話せる人がいない」という方は、
日記に気持ちを書いてみたり、AIに話してみるのも効果的ですよ。
2. ちょっと気分転換
仕事終わりや休日に好きなことをして気分をリフレッシュ。
- 好きな音楽を聴く
- アロマやお風呂でリラックス
- 美味しいごはんを食べる
- 本やドラマに没頭する
「楽しい」と思える時間が、こころの回復につながりますよ。
3. 身体を動かす
散歩やヨガなど、
軽めの運動はストレスホルモンの分泌を抑え、
気持ちを落ち着かせてくれます。
通勤時に一駅分歩くだけでもOKですよ。
ちなみに私はよくジョギングをしています!
4. ゆっくり深呼吸
緊張していると、呼吸は浅くなりがちです。
おすすめの呼吸法は
「4秒吸って、6秒吐く」こと。
数回繰り返すだけで、
副交感神経が働き、気持ちが落ち着いていきます。
5. 環境を整える
部屋が散らかっていると、こころまでソワソワしてしまいます。
- デスク周りを片づける
- 床に落ちているものを拾う
- 布団やベッドを整える
- トイレやお風呂掃除をする
「小さな模様替え」が、気分を大きく変えてくれることもあります。
STEP3|ストレスの根っこと向き合う「問題焦点型コーピング」
1. 現状把握
「何をつらいと感じているのだろう?」
ストレスの原因を具体的に書き出してみましょう。
例:
- 上司の言っていることが頻繁に変わる
- チーム内の連携が悪い
- 毎月の残業が40時間超えている
- パートナーが協力的ではない
原因を見える化することで、対処しやすくなります。
2. 適切に境界線をひく
「断る勇気」も自己防衛のひとつ。
「今の業務で手一杯なので、〇〇までなら可能です」
と、具体的に伝える工夫が有効です。
3. 信頼できる人に相談する
同僚や先輩、職場の相談窓口など、
信頼できる人に相談してみましょう。
ひとりで抱えないことが、もっとも大切です。
4. スキルアップや転職活動
職場や仕事内容が大きなストレスなら、
思いきって環境をがらりと変えることで
良い方向に進むことがありますよ。
がんばるあなたに—忘れないでほしいこと—
ここまで読んでくださったあなたに、
ありきたりですが、いちばん伝えたいことがあります。
それは、「あなたはすでに、よくがんばっている」ということ。
「十分がんばっているんだ」と
自分にはなまるをあげてください◎。
専門家に頼るのも、大切なコーピング
- 会社の相談窓口
- 地域の保健センター
- 心療内科やメンタルクリニック
今はメンタルの不調で誰かに相談することがあたりまえの時代になっています。
どこのクリニックに行けばいいのかわからないという場合は、地域の保健センターに連絡すると丁寧に教えてくれますよ。
まとめ|あなたのこころをストレスから守るために
- コーピングとは、ストレスと上手に付き合う方法のこと
- コーピングには「情動焦点型」と「問題焦点型」の2種類がある
- 自分のストレスサインに気づくことから始めよう
- できることを、少しずつ。
- 必要なときは、専門家に頼ることも大切。
自分を大切にすることはあたりまえのようで、とても難しいことですよね。
私もついつい忘れがちなので、意図的に読書に没頭する時間をつくったり、丁寧にコーヒーを淹れたり、身体を動かす時間をつくるなどのセルフケアを行なっています。
また、なんとなくこころが疲れてきたなと感じたら、いつでも「ゆるケア」に戻ってきてくださいね。