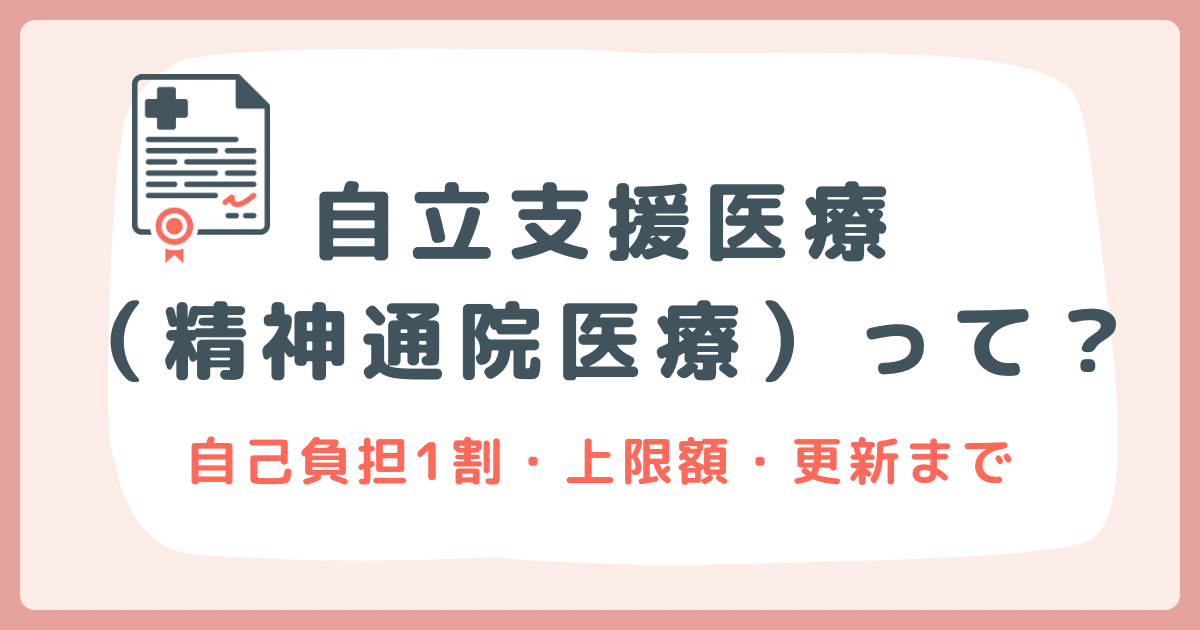ゆるぴー
ゆるぴー精神科に通っているんだけど、とにかく診察料とお薬代が高くて困ってます…



ゆるぴーさん、主治医の先生から「自立支援医療」について聞いていませんか?



じりつしえん…?なんですか?



この制度を使えば、医療費が1/3か、それよりも低くなるかもしれませんよ



えー!1/3もですか?
その「じりつなんとか」について、教えてください!
自立支援医療(精神通院医療)とは?|対象・範囲・自己負担
「毎月の精神科通院とお薬代、そろそろ厳しい…」
そんな不安を少しでも軽くするための公費負担制度が自立支援医療(精神通院医療)です。
メンタルの不調により継続的な通院治療が必要な方の医療費自己負担を軽減します。
対象は、統合失調症、うつ病・双極性障害、不安障害、PTSD、てんかんなど広く精神疾患が含まれます。
医療の対象範囲は入院を伴わない精神科の通院治療で、通院による診療、お薬、デイケア、訪問看護などが含まれます。
逆に、入院費や、保険がきかないとなるカウンセリング等は対象外です。
自己負担は基本の3割から原則1割へ軽減され、さらに世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が設定されます。
費用が高額になりやすい治療を続ける方(「重度かつ継続」に該当)には、別枠の上限額が設けられ、負担が一段と抑えられます。
申請の前に知っておきたい基本(期間・医療機関・注意点)
受給者証の有効期間は
原則1年です!
交付される受給者証の有効期間は1年以内。
引き続き利用する場合は更新手続きが必要で、多くの自治体で有効期限の約3か月前から申請受付が始まります。病状や治療方針に変更がなければ、診断書は2回に1回省略できる場合があります(自治体に確認しましょう)。
利用できるのは
指定自立支援医療機関のみ!
軽減が受けられるのは、都道府県・指定都市が指定した指定自立支援医療機関に限られます(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)。
受診先が指定かどうかは、医療機関や薬局で直接確認できます。
よくある勘違い
入院費は対象外(通院が対象です!)
入院を伴わない通院治療が対象となります。
その他、心理カウンセリングなど、保険適用外の費用は対象になりません。
申請方法と必要書類|迷いやすいポイントまとめ
申請はお住まいの市区町村の担当窓口(福祉課など)で行います
流れの(例)
- 主治医に自立支援医療の診断書を依頼する
- 市区町村の窓口で申請書提出(本人/代理可)する
- 審査・決定 → 受給者証と上限額管理票を受け取る
- 医療機関や薬局で受給者証と上限額管理票を提示する
必要書類(自治体により差あり)
- 申請書(窓口または医療機関で入手できることも)
- 医師の診断書(「重度かつ継続」の場合は様式が異なることあり)
- 健康保険証(世帯の加入関係が分かるもの)
- 市民税の課税(非課税)証明や収入確認書類(必要に応じて)
- マイナンバー確認書類
※ 窓口の同意で一部書類が省略できる場合があります。
節約効果はどれくらい?
毎月の医療費が高めの人|上限額で節約効果大
1割負担でも通院頻度や処方数が多いと負担は大きくなりがち。
そこで月ごとの自己負担上限額が役に立ちます。所得区分ごとに上限額が定められ、非課税世帯では低い上限が設定されています。
お薬代が中心の人|薬局でも使えるの?
もちろん使えます!精神科のお薬って高いですよね…。
指定医療機関の薬局であれば、お薬代も1割負担になりますよ。
受給者証と管理票の提示を忘れずに。
デイケア・訪問看護を利用する人も
精神科デイケアや訪問看護も対象です。
継続的なリズムづくりや再発予防と合わせて、費用面の後押しにもなりますよ。
申請を迷っているあなたへ
◯主治医になんて相談すれば良い?



でも、主治医から何も言われてないし、なんて相談したらいいかわからない…
そんな方のために、そのまま使えるセリフを用意しました。
下記の文章をスマホや紙にメモして、次の通院のときに相談してみましょう。
言葉で伝えることが不安な方は、このスマホでこのブログを主治医の先生に見せてみましょう!
【主治医の先生に伝えること】
「通院費が少し負担で…。調べたら自立支援医療というものがあると聞いたので、診断書を書いてほしいです。その他に必要な情報があれば教えてください…!」
診断書は病院の混み具合で時間がかかることも。早めに相談するとスムーズですよ。
申請後にやることチェックリスト
- 受給者証が届いたら、次回の通院から必ず提示する
- 上限額管理票も一緒に持参する
- 通う可能性のある薬局・訪問看護が指定医療機関か確認する
まとめ|まずは「診断書の相談」と「自治体窓口の確認」から
自立支援医療は、1割負担+月ごとの上限額で、精神科の通院治療にかかる自己負担を抑える制度です。
対象疾患は幅広く、通院・お薬・デイケア・訪問看護までカバー。
申請は市区町村で、受給者証は1年ごとに更新——手順をひとつずつ進めれば大丈夫。
最初の一歩は、主治医へ診断書の相談と、お住まいの窓口の必要書類の確認から。
お金の負担が少しでも減って、あなたが治療に専念できることを願っています!